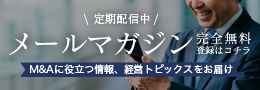【朝礼で活きる経営者の名言・格言】革新的な商品を生み出す「安藤百福」

メーカーにとって革新的な商品を世に送り出すことは、一つの本懐といえます。その夢を叶えるには、熱意を持って挑戦できる環境に加え、社員の創意工夫が必要不可欠です。
日清食品の創業者である故・安藤百福氏の言葉は、新商品を作る開発者が奮い立つ起爆剤となります。安藤氏は経営者であると同時に「チキンラーメン」と「カップヌードル」の開発者。世界初のインスタントラーメンを作り出し、世界の食文化にイノベーションを起こしました。
安藤氏の商品開発にかける情熱を、チキンラーメンとカップヌードルの開発秘話と合わせて、社員に伝えてみてください。商品開発へのモチベーションが高まり、アイデアが飛び交う組織へと成長することでしょう。
目次
「開発者にとって一番大切なのは創造力である」
いくつもの事業で失敗してきた安藤氏。1957年、当時47歳だった安藤氏は、理事長を務めていた信用組合が破産し財産が没収されてしまいました。ただ、安藤氏は「失ったのは財産だけではないか。その分だけ経験が血と肉になって身についた」と前向きに考え、無一文でインスタントラーメンの開発に乗り出します。
研究所は知り合いの大工に建ててもらった10平米ほどの小屋で、人手もなく、自身も麺については素人。そんな中で安藤氏は「美味しくて飽きないこと」「調理に手間がかからないこと」など5つの目標を掲げ、お湯があればすぐに食べられる麺を目指しました。無い無い尽くしの中でも安藤氏には明確な理想があったのです。
当然それは前例がなく、製法もまったくの未知。開発は困難を極めます。しかし、試行錯誤の末にチキンラーメンは完成に至ります。キーとなったのは「瞬間油熱乾燥法」の発見でした。これは天ぷらの調理法を応用した技術で、安藤氏の奥様が天ぷらを揚げている姿を見て着想を得たそうです。
その経験からか安藤氏は「資金や設備がなくても研究開発はできる」と強調しています。さらに「IT全盛の時代になっても、開発者にとって一番大切なのは創造力である。それを、やり遂げる執念である」と若い開発者に言い続けました。設備や技術力よりも、アイデアと努力。つまり開発者の創造意欲こそが、革新的な商品を生み出す源泉なのです。
朝礼で伝えたいポイント:開発は“1日にしてならず”
・「お金や技術がないから……」は言い訳にすぎない
・商品のコンセプトは理想から逆算して設計する
・どんなのに開発が難しくても、工夫を凝らして形にする
朝礼での活用例
おはようございます。突然ですが、皆さんはインスタントラーメンを食べたことはありますか? きっと、ほとんどの人が一度は口にしたことがあると思います。私も好きで、よく食べています(笑)。
世界ラーメン協会によるとインスタントラーメンは2020年には世界で約1166億食が消費されたそうですが、すべては日清食品の「チキンラーメン」から始まりました。1958年に、日清食品の創業者である安藤百福さんが開発し、「魔法のラーメン」と評されるほどの大ヒットを遂げたのです。
しかし、なんと当時、安藤さんは一文なし。設備も麺作りの知識もなかったのです。有ったのはインスタントラーメン開発にかける情熱と理想でした。「美味しくて飽きがこないこと」「保存性が高いこと」「簡単に調理できること」「安いこと」「安全で衛生的であること」という、当時の常識では考えられない5つの目標を掲げたのです。
当然、開発は困難を極めます。しかし、安藤さんはあきらめませんでした。道具や材料は自分で集め、睡眠時間1日平均4時間。1日も休まずに、たった一人で研究を続けました。そんな中、安藤さんの奥様が天ぷらを揚げているのを見て、油熱を利用した乾燥法を思いつき、チキンラーメンの完成に至るのです。
そのため、安藤さんは何度も「資金や設備がなくても研究開発はできる。開発者にとって一番大切なのは創造力である。それを、やり遂げる執念である」と語っていたそうです。
皆さんも、もし実現が困難なアイデアが浮かんでも「資金がないから難しい」「技術がないから不可能」とあきらめないでください。思い描いた商品が実現したら、世界を変えられるかもしれない。ぜひ、そんな心持ちで商品作りに取り組んでください。
「身の回りの至る所に発明のヒントがある」
瞬間油熱乾燥法をはじめ、安藤氏は生活の中からアイデアを思いつくことが多くありました。インスタントラーメンを作ろうと思ったきっかけも同様でした。戦後まもない頃、冬の夜にラーメンの屋台に人が並んでいるのを見て「大きな需要が暗示されているのを感じた」からだと振り返っています。
カップヌードルの開発も、欧米視察旅行での一幕から着想を得ました。ロサンゼルスのスーパーでバイヤーがチキンラーメンを試食する際、麺を入れる丼がありませんでした。彼らは仕方なくチキンラーメンを半分に割って紙コップに入れて食べ始めたそうです。
安藤氏は、欧米では箸と丼で食事をしない、という当たり前のことに改めて気がつきました。そして「美味しさに国境はない」という考えから「超えるべき食習慣の壁がある」と認識を改めたのです。この気づきから「即席麺を世界商品にするには、麺をカップに入れてフォークで食べられるようにしよう」と決心。カップヌードルの開発に取り掛かります。
新しい商品を開発しようとすると、専門的な部分に目がいきがちです。その勤勉さは美徳ですが、それだけではユーザーが喜ぶ商品は作れません。何気ない日常の一コマに目を向け、実際の生活からニーズを発見することが大切です。
朝礼で伝えたいポイント:常に周囲に好奇の目を向ける
・ヒットした商品、サービスから人気の理由を探る
・ユーザーの需要や不便を見逃さないよう常にアンテナを張る
・商品を開発する際は、ユーザーの実情や生活を考慮する
朝礼での活用例
私から皆さんに質問です。商品について考えるとき、どのようにしていますか? 色々な考え方があると思いますが、今回はその一つの答えとして、カップヌードルを作った安藤百福さんの言葉を伝えたいと思います。
「身の回りの至る所に発明のヒントがある」
日本だけでなく世界の食文化を変えたアイディアマンである、安藤さん。その発想の源は日常の中にあったというのです。
その具体例が、前述のカップラーメンです。安藤さんが欧米視察の一環で訪れたロサンゼルスのスーパーマーケットで着想を得ました。アメリカ人バイヤーがチキンラーメンを試食する際に丼がなく、チキンラーメンを半分に割って紙コップに入れて食べ始めたのです。
この一幕を見て安藤氏は「麺をカップに入れてフォークで食べられるようにしよう」と思い付きました。バイヤーからすると何気ない行動だったのでしょうが、安藤さんにとっては値千金の情報となったのです。
皆さんはプロとして専門的な知識を持っていると思います。しかし、それだけでなく周囲の人や日常の光景にも目を光らせてみてください。そこにはユーザーのニーズや現実があり、皆さんに血肉の通った素晴らしいアイデアをもたらしてくれるはずです。
「私は自分の肌で感じた感覚を大事にしているが、客観的なデータももちろん大切にしている」
安藤氏は「細心大胆」をモットーにしていました。商品開発においても自分の目と肌が感じた直感と、データに従う客観性を両立。自分の信念を貫くだけの「一人よがり」にはならず、他人の意見を上手に受け入れて「皆が望む理想の商品」を作り上げていったのです。
そのバランス感覚は、1970年のアメリカ日清を設立した際に遺憾なく発揮されました。アメリカでインスタントラーメンが売れるか市場調査すると「アメリカ人は動物性タンパク質を好むから、でんぷん主体の麺類に成長性はない」という結果が得られました。社員に聞くと「欧米人は猫舌で熱いものが食べられない」と否定的な意見も多数あがりました。
そこで安藤氏は、すぐにアメリカ向けに開発した「トップラーメン」をロサンゼルス近郊のスーパーマーケットで試食販売します。消費者の反応を確かめると「デリシャス」と好評で、一週間後に再販すると何人もの主婦が「美味しかった」と再購入したのです。一連の光景に安藤氏は自信を深めました。
安藤氏が素晴らしかったのは、さらにそこから。後にアメリカで発売した「カップ・オ・ヌードル」でビーフ、チキンなど動物性タンパク質を入れ、麺の長さを半分にして猫舌で麺がすすれないアメリカ人でも食べやすいよう工夫したのです。
重要なのは、多角的な視点からユーザーの本質を捉えること。自分の直感を信じながらもデータを有効活用することで、真にユーザーが喜ぶ商品を開発できるのです。
朝礼で伝えたいポイント:直感を前提にデータを重視する
・データを盲信せず、自分の目と耳でも情報を集める
・反対意見にも耳を傾け、参考にして活用する
・直感とデータを融和させ、ユーザーの本質を捉える
朝礼での活用例
本日は私が尊敬する日清食品の創業者、安藤百福さんの言葉を贈ります。
「私は自分の肌で感じた感覚を大事にしているが、客観的なデータももちろん大切にしている」
どっちつかずじゃないか!と言いたくなりますね(笑)。しかし、この言葉の裏には「ユーザーニーズは多角的に捉えるべき」という、重要なエッセンスが詰まっています。
例を出しましょう。1970年に安藤百福さんは、アメリカでインスタントラーメンを売るために市場調査をしました。その結果、「アメリカ人は動物性タンパク質を好むから、でんぷん主体の麺類に成長性はない」というデータが得られました。それでも安藤氏は、お客様の意見を自ら再調査。ロサンゼルス近郊のスーパーでアメリカ向け商品である「トップラーメン」の試食販売を実行したのです。
安藤さんは最初の市場調査データに納得がいかなかったのです。その直感通り、インスタントラーメンの試食販売は大好評。安藤さんはアメリカでの成功を確信しました。
ここまでならよくある話でしょう。しかし、安藤さんが素晴らしかったのは、市場調査での否定的なデータをそのまま切り捨てなかったこと。後にビーフやチキンなど動物性タンパク質を入れた「カップ・オ・ヌードル」をアメリカで発売したのです。
良いアイデアが浮かぶと自分の直感を信じたくなりますし、客観的なデータがあれば頼りたくもなります。しかし、決してどちらかに偏ることなく、多角的な視点を持ち続けてください。そうすることで、ユーザーの本質をつく開発力が身につくはずです。
開発者の情熱が商品と企業に革新をもたらす
91歳の時に宇宙食ラーメンの開発にチャレンジした安藤氏。晩年まで開発者としてあり続けた氏の言葉は一見シンプルに聞こえますが、彼の人生を知れば知るほど心に染み込んできます。一朝一夕では生まれない“インスタントではない足跡”が説得力を生んでいるのです。
偉大なる開発者の生き様が社員に注入されれば、社員が成長し、職場も活気づくはず。革新的な商品を生み出す第一歩として、安藤氏の言葉を伝え、組織の意識改革を図ってみてはいかがでしょうか。
日清食品創業者。日本即席食品工業協会や世界ラーメン協会の会長も務める。台湾で生まれ、戦前は大阪で集荷・問屋業を営む。戦後は食品商社「中交総社」を設立。世界初のインスタントラーメン「チキンラーメン」を発明し日清食品を創設した。1971年には世界初のカップ麺「カップヌードル」を発売。日清食品グループを世界的な企業へと成長させた。
参考図書
「魔法のラーメン発明物語 私の履歴書」安藤百福|日本経済新聞出版
「転んでもただでは起きるな! 定本安藤百福」安藤百福発明記念館|中公文庫
「安藤百福の思い」|日清食品グループ
「安藤百福クロニクル」|日清食品グループ